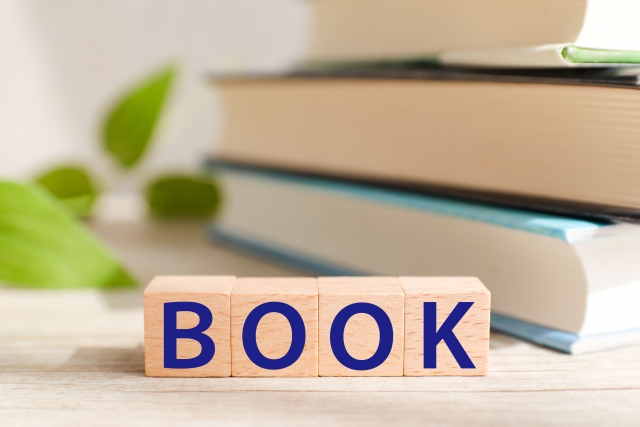
様々な種類の宝石を紹介する本は、ジュエリー本の基本です。
本屋の理工学コーナーの中にある、地質学や化石、または鉱物学と区分された場所には、必ずそういった内容の本がありますよね。
私もこれまで、いろいろな宝石紹介本を読んできました。
どれもこれも美しい写真と、私の知らない宝石情報に溢れていて。
オリジナルの切り口での分類や、宝石雑学の一言コメントも面白い。
どれも甲乙つけがたい書籍ばかりです。
そんな中、今回は私が選んだわけではない「宝石紹介本」を一冊、おすすめします。
またもや、子供向け書籍。
でも、この本は、私にとってはものすごくツボな本でした。
親戚の小学生が図書館で見つけた本
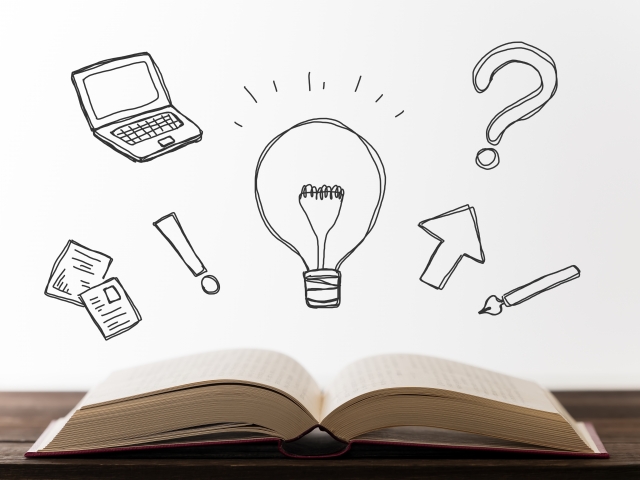
今回、「みんなが知りたい!宝石のすべて」を手にした理由は、小学三年生の姪がたまたま図書館で借りてきたからです。
私が自分で見つけた訳ではありません。
姪は私が宝石の仕事をしているのを知っているので、図書館で見つけた「みんなが知りたい!宝石のすべて」を、嬉しそうに私にみせに来てくれました。
もしかすると、わざわざ図書館に行って、私のために宝石の本を探してくれたのかもしれません。
……とか言うと、なんだか幸せな光景が目に浮かぶでしょう?
実際は、そうではないんです。
彼女は私の前にくるなり、無邪気な笑顔で、
「では、問題でーす!」
と。
それでは、皆様もご一緒に「問題」を解いていきましょう。
問1:ダイヤモンドの屈折率は?
問2:ルビーの比重は?
問3:エメラルドの主な産地を5つ!
問4:アメシストの化学組成は?
問5:真珠の結晶系は?屈折率は?
…………ええ、頑張りましたよ。
終わりのない宝石学一問一答。
単純だけど、ほとんどが記憶力に頼る問題なので、覚えていないとどうしようもない。
そもそもですよ。
結晶系なんて言葉、小3は知らないでしょ!
鉱物の化学組成なんて、あんなん完璧には覚えてないしっ!!
真珠の屈折率なんて、真珠を痛めるのが嫌だから、ほとんど計ったことないよ!!!
と、心の中で叫びつつ、資格持ちのおばさんの威厳を保つために必死に記憶の引き出しを引っ張る。
そんな地獄の小一時間でした。
勉強ってずーっと続けないといけませんね。
知識は生もの。
直ぐ腐る。
読みやすい!結晶系ごとに分類分けされた宝石紹介本

こうして、突如始まった宝石学テスト(面接方式)は、かろうじて合格したのですが。
その後、彼女にお願いしてその本を見せてもらいました。
内容は、よくある宝石紹介本と大きな差はありません。
小学生向けなので、全ての漢字にルビがふっていて、更に内容も読みやすくなっています。
でもこの本の最大の特徴は、子供向けであることではありません。
この本で紹介されている宝石たちは、結晶系別に分類分けされているんです。
結晶系と言えば、宝石学を学ぶ上では避けて通れない最初のつまずきポイント!
初めの授業で説明された時は、1日考えて、その結果「うん、わからん!」となった良い思い出があります。
そんな結晶系は、宝石学、つまり鑑別をする上でとっても重要な知識です。
絶対理解しないといけないし、どの宝石がどの結晶系に属するのかもよく知っておく必要があります。
つまり、この本は、
ルビつき&比較的易しめの言葉。
更に、結晶系という私の苦手範囲に焦点を当てた、分類方法。
これはもう、買うしかありませんね!
結晶系を知れば手元の宝石が今までと違った見え方になる

ところで、結晶系とは?
これは詳しく書きだすと(私のように)混乱と絶望がやってくるので、簡単に説明したいと思います。
鉱物というのは、一定の化学組成を持っています。
ですが、化学組成だけでその物質が分類できる訳ではありません。
重要なのは、その鉱物を構成する元素がどのように並んでいるか。
例えばダイヤモンドだったら、炭素なので「C」で出来ている。(実際にはもうちょっと複雑ですが、とりあえずここでは炭素単体だけで出来ていると仮定します)
炭素という物質が、ある一定の規則正しい配列で並ぶことで、炭素はダイヤモンドという鉱物になります。
「一定の規則正しい配列で並ぶ」
↑
この並び方というものは、いくつかの種類に分類できます。
この分類が、結晶系。
ダイヤモンドの場合は、等軸晶系という結晶系。
ちなみに、同じ炭素で出来ているグラファイト。
これもダイヤモンドと同じで「炭素が一定の規則正しい配列で並んで」いますが、ダイヤモンドとは並び方が異なります。
つまり、結晶系が異なるんですね。
グラファイトの場合は、六方晶系。
同じ物質で構成されていても、結晶系が変わると見た目も性質もまるで異なる鉱物が完成するんですよ。
このように、鉱物と結晶系は切っても切れない深い関係でつながっています。
結晶系を肉眼で楽しむには?
とはいえ、こんな化学の話をされても、鉱物オタク以外は何も面白くないですよね。
実際いろいろな宝石紹介本に各宝石の結晶系は記載されていますが、普通はスルーされる内容です。
でもね、この結晶系、実は肉眼でも十分に楽しむことが出来る代物なんです。
一番わかりやすいのは、鉱物標本。
水晶の結晶で、先が尖ったものを見たことありませんか?
あの一番先の部分。あれはカットして生み出すものではありません。
あれこそが水晶の結晶が作り出す、自然の芸術品。
尖った部分をよく観察すると、単純に尖っているだけではなく、いくつかの三角で構成されているのが分かります。
他にも、アクアマリンやエメラルドの結晶は、まるで削る前のまっさらな六角鉛筆のような形になっています。
あれも、肉眼で見える結晶系の姿ですね。
これらの鉱物標本の外形は、(鉱物が調子よく成長していれば)その鉱物が所属する結晶系の形状に従い、形成されています。
ダイヤモンドと、スピネル、そしてフローライト(蛍石)。
この三つは化学組成はまるで異なりますが、同じ等軸晶系に属する鉱物。
だから、三つとも基本的な原石は八面体でしょう?
結晶系は全部で6個と覚えておけばいい
結晶系に、興味が出てきましたか?
では、ここで宝石学で学ぶ6つの結晶系を紹介していきます。
①等軸晶系(立方晶系)
②正方晶系
③三方晶系/六方晶系
④直方晶系(以前は斜方晶系と表記していました。現在は直方晶系が正式な呼び名です)
⑤単斜晶系
⑥三斜晶系
(③の三方と六方は、それぞれ別の結晶系であると数える場合もあります)
で、ここからは宝石学というよりも、結晶学という別の学問。
これらの結晶系は、対称軸の数や長さ、角度によって分けられています。
①なら、対称軸が3本、軸角度はどれも90°、軸の長さは3軸等長。
最も対称性の高い結晶系です。
②の場合は、対称軸が3本、軸角度はどれも90°、軸の長さは2軸等長・1軸不等長。
③の場合は、対称軸が4本、軸角度は3軸が交互に60°・1軸(C軸)は90°、軸の長さは3軸等長・C軸不等長。
って、意味が分からないでしょう?
私もそうでした。
というか、今でも時々混乱します。
対称軸って何!? 軸ってどこにあるの!? ってね。
だから、もう細かいことはどうでもいいんです。
宝石の結晶系は6種類!
これだけ覚えておけば、後は何とかなります。
結晶系ごとに宝石をみれば新しい見え方もみつかるかも!?

結晶系の話を詳しくし語りだすと、本当にヤヤコシイです。
未だに私も完全には理解しきれていないと思います。
記憶力も怪しいですしね。
でも、宝石を好きになったなら、一度は結晶系について調べてみるのも面白いですよ。
結晶系は、沢山ある鑑別知識の第一歩。
理解できれば、宝石店やミネラルショーでの宝石の「見方」も変わるかもしれません。
というわけで。
宝石の結晶系を学ぶ第一歩に、「みんなが知りたい!宝石のすべて」をおすすめします。
「みんなが知りたい!宝石のすべて きれいな石の成り立ちから美しさのヒミツまで」
著者:「宝石のすべて」編集室
